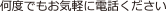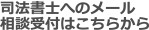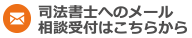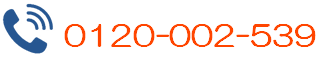相続よもやま話〈2025年〉
~毎月1回お届けする相続に関する楽しいイラスト付きエッセイ風コラム~
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
目次
(2025年12月) ペットの「終活」も忘れずに
(2025年11月) 土地の詐欺を狙う「地面師」
(2025年10月) 法律を陰で支える「公証役場」
(2025年9月) 都市と農村で戸籍が違う中国
(2025年8月) お盆と「死後離婚」の話
(2025年7月) 複雑な長嶋家の相続問題
(2025年6月) 相続税はどれくらい?
(2025年5月) 相続したくない財産
(2025年4月) 中小企業の事業承継
(2025年3月) 神戸市の『樹林墓地』計画
(2025年2月) 国籍と夫婦別姓問題について
(2025年1月) 『エンディングノート』あれこれ
(2026年当月~1月) 目次
(2024年12月~1月) 目次
(2023年12月~1月) 目次
(2022年12月~1月) 目次
(2021年12月~1月) 目次
(2020年12月~1月) 目次
(2019年12月~1月) 目次
(2018年12月~1月) 目次
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年12月】
ペットの「終活」も忘れずに
ペットロスということがよく言われます。長年可愛がっていたペットが亡くなると飼い主は大きなダメージを受けてしまい、その影響で精神的かつ身体的な不調に陥るケースが多いようです。今やペットは私たちの生活にそれほど深く関わっています。
社団法人ペットフード協会の調査によると、2024年のわが国の犬猫の飼育頭数と飼育世帯数は、犬が680万頭で515万世帯、猫が916万頭で506万世帯となっています。それぞれの飼育世帯の割合と平均飼育頭数は、犬が8.8%で1.3頭、猫が8.6%で1.8頭という結果です。ここ10年ほどで犬はやや減っていますが、猫は世帯の平均頭数が多いことにも表れているように増える傾向にあります。
またそれぞれの平均寿命は、犬が10~15年、猫が12~16年で猫の方が若干長生きです。その年数は、ここ10年ほどの間に人間と同じく1年ほど延びています。
ペットが飼い主より先に死ぬとペットロスが起きますが、逆に飼い主が先に亡くなってしまうとペットが取り残されることになります。家族で飼育している場合は別として、一人暮らしの場合はペットだけが残ります。そうなると、その世話や処遇を巡って困った事態が起こります。
こうした場合に備え、残されたペットについて誰にどのようなことを依頼するか遺言に明記する人もいるようです。しかし現実問題として、親族や知人などでそれを快く引き受けてくれる人がいるとは限りません。

以前(2020年10月)にこのコラムで「負担付贈与」という方法について記したことがあります。これは何らかの負担をしてもらうことを条件に誰かに財産を贈与するというもので、この場合はペットの飼育や世話をしてもらう代りに、その人に財産を贈与します。ただ注意しなければならないのは、この遺贈(遺言による贈与)は相手の承認がなくてもできるため、後で相手がそれを拒否することも考えられます。
それを防ぐには、贈与を受ける人との間にきちんとした取り決め(契約書など)を交わすことが望まれます。それにより、安心してペットの面倒を見てもらうことが可能となります。
とは言えそのペットがいつまでも元気であるとは限らず、毎日の食事や散歩の他に、病気治療のため通院や入院をしなければならないこともあります。あるいは世話ができなくなり、引き取ってくれる人を探さなければならないかもしれません。
しかし現在は保護施設等の中で犬猫があふれている状態で、これもそう簡単な話ではありません。さらに死んだ後はお葬式を上げたり、どこかに埋葬してもらう必要もあるでしょう。
近年はこうした問題を解決するため、ペットの引き取り活動を行なったり譲渡先を探したり、あるいは終生の飼育サービスを提供している民間業者もあるようです。そうした業者から適切な所を選ぶのも良い方法かもしれません。いずれにしてもペットを飼育している高齢者は、自分のことだけでなくペットの「終活」もぜひ忘れずに行って頂きたいものです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年11月】
土地の詐欺を狙う「地面師」
先月は法律を陰で支える公証役場の話をしましたが、今月はそれとは逆に法律を裏からすり抜けようとする「地面師」の話をしたいと思います。
先日のNHKスペシャル「未解決事件」の番組で、2017年6月に大手ハウスメーカーの積水ハウスが「地面師」グループに土地の購入代金として55億円余りをだまし取られた詐欺事件のことが放送されていました。
事件そのものはそれほど新しい話ではなく、17人が逮捕され捜査は終結していますが、今年になってNHKに服役中の主犯格とされる男から「黒幕は別にいる」との手紙が届き、まだ完全に真相が明らかにされたとは言えないため未解決事件として取り上げられたものです。
事件の舞台となった山手線五反田駅から徒歩3分の旅館「海喜館(かいきかん)」は、かねてから不動産業界では注目の案件でした。積水ハウスはその所有者を名乗る女と、約600坪の旅館敷地を70億円で購入する売買契約を締結。売買の窓口となった仲介会社に所有権移転の仮登記、さらに積水ハウスに移転請求権の仮登記がなされました。そして売買代金70億円のうち63億円を支払い、直ちに所有権移転登記を申請しました。しかし本来の所有者がいたことで、登記所が積水ハウスの売買予約に基づく仮登記を認めませんでした。この時点で積水ハウスは地面師グループにだまされたことになります。

「地面師」とは、架空の売却話を持ちかけて代金をだまし取る詐欺を行う者たちを指します。彼らは複数人で役割を分担し、巧妙な手口で詐欺を実行します。その手口の基本は、不動産の真の所有者や相続人になりすますことです。
そして巧妙に偽造された登記簿謄本、権利証、印鑑証明書、身分証明書などを悪用し、取引が正当であるかのように見せかけます。身分証明書に「なりすまし」の顔写真を使い、本物そっくりに偽造することもあります。さらには弁護士や司法書士などの専門家をグループに加担させることもあるため、詐欺を見抜くのがなかなか難しいのです。
「地面師」の言葉は「地面(=土地)詐欺師」の略で、戦後の混乱期に空襲による書類焼失や登記所の混乱、人員不足などが重なり、不動産の権利関係が不明確になった時期に始まります。その後の昭和期にはバブルで地価が高騰し、多くの企業や投資家が被害に遭いました。それが今だに続いていることが、この積水ハウス事件で明らかになったわけです。
「地面師」に狙われやすい不動産には、長期間利用されていない更地や空き地、所有者が高齢で管理が行き届いていない物件などがあるとされます。最近は土地や不動産に関すること以外にも、様々な詐欺事件が多発していますので、私たちも日頃から十分に注意して被害を未然に防ぎたいものです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年10月】
法律を陰で支える「公証役場」
名前はよく耳にしますが、私たちが一生のうちで「公証役場」に足を運ぶ機会はそれほど多くないと思います。このようにふだんはあまり関わることのない「公証役場」ですが、法律的なことについてはそれなりに重要な役割を果たしています。
例えば相続の遺言書作成において、よく自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類あると言われますが、この公正証書遺言とは公証人が「公証役場」で作成するものを指します。さらに安全に保管してくれるため裁判所での検認も不要となり、遺言の方法としては最も確実とされています。
公正証書とはある人が法的に意味のある行為をしたという事実を証明する文書のことで、公正証書として代表的なものは前述の遺言公正証書や契約公正証書などがあります。
すなわち遺言公正証書とは遺言者の遺言内容を記載した公正証書のことで、契約公正証書とは当事者間の契約内容を記載した証書を指します。
公正証書が広く用いられる契約の一つとして、不動産取引があります。例えば日本では事業用定期借地権を設定する契約は、公正証書によらなければならないとされています(借地借家法23条)。
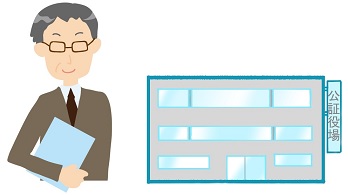
このような公正証書を作成する役場が「公証役場」で、その証書を作成するための公的資格を持つ専門家が公証人です。そして遺言公正証書のような原本を「公証役場」で保管してくれるので、その存否や瑕疵の有無が争われる可能性が少なく、法律上高い証明力を有しています。
公証人は公証人法に基づいて法務大臣が任命する公務員で、それを所管するのは各法務局です。ただし法務省などから給与や補助金を受け取ることはなく、公定された手数料を依頼人から受け取って収入としています。このような独立採算制が採られていることが、一般の公務員と異なる大きな特長です。
公証人は、全国各地の「公証役場」で公正証書の作成や定款の認証などを行っています。現在全国で「公証役場」は約300ヶ所、公証人は約500名おり、近年は新しい電子定款認証に対応する指定公証人の配置も進められています。
このように私たちの法律的な手続きを陰で着実に支えてくれている全国の「公証役場」と公証人の方々の日頃の努力に、大いに感謝したいものです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年9月】
都市と農村で戸籍が違う中国
相続と関連するわが国の戸籍制度については、本コラムでも何度か取り上げています。しかし同じような家族中心の戸籍制度を導入している国は意外に少なく、中国(中華人民共和国)と台湾(中華民国)のみです。
韓国では同じような制度がありましたが、儒教の影響による家父長的制度は男女同権に反するということで2008年に廃止されました。
ちなみに欧米諸国では「個人登録制度」が主流で、基本的に個人別あるいはその身分変動時に登録して証明する制度となっています。そして家族関係を証明したい場合は「出生証明書」「婚姻証明書」などを利用して行います。
わが国と同じように家族の戸籍制度を採用している中国ですが、実は都市戸籍と農村戸籍の区別があります。これは農村から都市への人口流入を抑制する目的で、1958年に二元的な管理制度として確立されました。そしてそれぞれの社会保障や公共サービスの内容は、大きく異なっています。
都市戸籍は都市部で生まれた人が登録され、教育や就職、医療、社会保障など多くの面で優遇されており、不動産取得や公立学校への入学でも有利になっています。
これに対し農村戸籍は、農地の割り当てがあるものの社会保障は不十分で、子供の義務教育を含む公共サービスが受けられなかったり、失業保険の給付対象にならない場合があるなど、大きな格差があります。

近年わが国においても人口減少や労働力不足などから外国からの移民問題の議論が盛んですが、すでに多くの外国人が居住する地域もあります。その一つが埼玉県川口市で、中国人やクルド人が多いことで知られ、外国人居住者は人口60万人のうち5万人を超えています。うち中国人は2万人以上で、特に西川口に集中してチャイナタウンを形成しています。そして彼らの多くは、中国の東北部出身の人たちと言われます。
中国では都市部の人の海外への進出先は欧米やオセアニアが人気ですが、東北部など経済的にやや遅れた農村地域ではチャンスを求めて日本に来る人も多いようです。
その理由として、農村戸籍から都市戸籍に切り替えできる機会が限られていることが挙げられます。大学卒業後に都市部の一定条件を満たす企業に就職した場合など、その機会はきわめて限定されています。
ようやく2021年に人口300万未満の都市に限り農村戸籍対象者の移住が認められることになりましたが、結婚しても都市戸籍や農村戸籍は変わらないため、その格差から抜け出すのは容易ではありません。
そのような格差に苦しめられている中国の農村戸籍の人たちにとっては、都市や農村で区別されないわが国の戸籍制度は自由で魅力的なものに映るのかも知れません。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年8月】
お盆と「死後離婚」の話
今年もまた猛暑の中、お盆の季節がやってきました。お盆とは仏教用語の「盂蘭盆会」(うらぼんえ)に由来し、ご先祖様を供養する行事を指します。東京など一部地域では七月に行うこともあるようです。京都ではお盆にこの世に帰ってきたご先祖様の霊を、あの世へ送り出す五山の送り火が八月十六日夜に行われます。
ご先祖様とは言うまでもなく「家」に関係する両親や祖父母などの血縁の一族を指し、お墓や仏壇などとも密接につながっています。これはわが国の「家」制度から生まれたもので、その歴史は江戸時代の武士の家父長的な家族のあり方をもとに明治時代に制度化されたと言われ、実は日本の歴史の中ではそんなに古いものではありません。
この「家」制度を支えてきたのは、言うまでもなく結婚(婚姻)とそれによって生まれる子供たちです。婚姻によって自分の血族の他に、配偶者の血族との間に新たな姻族関係が発生します。それらを含めて親族となります。親族は親戚や親類とも呼ばれますが、民法では6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族(配偶者の血族)を指します。
しかし近年は少子化・核家族化の進行で、この「家」制度が都市部を中心にしだいに形骸化しつつあります。かつての大家族は減って、少人数世帯が多くなりました。それに加えて離婚が増加し、人々が「家」を意識する機会も少なくなっています。

そんな中でさらに「死後離婚」というものまで注目されるようになりました。これは本コラムでも2019年8月に取り上げたことがあります。もちろん死後に離婚することはできませんので、きちんとした法律用語ではなくマスメディアの造語と言われますが、正式には『姻族関係終了届』の提出を指します。これにより、具体的には婚姻によって発生した3親等以内の姻族との関係が解消されることになります。
その主な理由は義父母とは同居したくない、介護をするのはいや、夫や義父母と同じ墓に入りたくない、といったものです。ただし姻族関係を終了させても、遺族年金の受給資格はそのままですし、相続財産を引き継ぐこともできますので、実質的にはあまり困ることはないのかもしれません。
これは配偶者の「家」とはもう関わりたくなく、それと縁を切りたいとの意思のあらわれと言えます。ただし姻族関係はすべて終了しますし、一度提出して受理されたものを元に戻すことはできません。また子供がいる場合、子供には配偶者を通じてその両親などとの血縁関係があり、それを解消することはできません。これは通常の離婚でも「死後離婚」においても共通しています。ですからまず子供の意思を確認することも大切と言えます。
こうした問題も含めて、はたしてそれが適切な判断なのかを慎重に考えてから結論を出して頂きたいものです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年7月】
複雑な長嶋家の相続問題
有名人の相続問題については、これまでも度々取り上げてきました。紀州のドンファンこと野崎幸助さんの死と相続に関する若い妻の疑惑については2024年7月に至るまで数回、また経済評論家森永卓郎さんの父の相続をめぐる大変な作業については2021年9月、作家石原慎太郎さんの婚外子を含めた子息たちの相続については2022年5月、ドリフターズのお笑い芸人仲本工事さんの内縁妻の話は2022年11月にそれぞれ記載されていますので、ご興味のある方はご覧ください。
有名人は遺産が高額となり、また家族を含めた人間関係が複雑になりがちです。それらが相続を難しくする大きな理由となっているようです。
さて今回は、かつてのプロ野球スター長嶋茂雄氏の相続の話ですが、その遺産総額ははたしてどれくらいなのでしょうか? まず長年住み続けた大田区田園調布の豪邸は、土地だけで7億円以上とのこと。また長嶋家の個人事務所「オフィスエヌ」所有の別の一軒家や二階建てテラスハウス、さらにマンションや別荘、自宅近くの二階建て家屋など他にも多数あるようです。これらの所有物件を合わせれば、土地だけでもゆうに20億円を超えると言われています。
それに加えて「オフィスエヌ」は長嶋氏の肖像権や商標権も管理しています。さらに氏は20年以上にわたり読売巨人軍の専務取締役に就いており、年間2000万円ほどの報酬を得ていました。それらを合わせると総額はさらに膨らむものと予想されます。
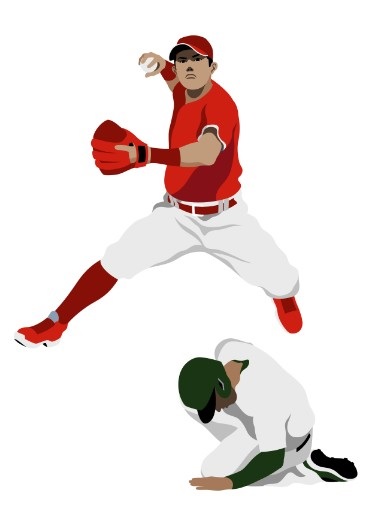
これらの遺産を相続するわけですが、茂雄氏の妻亜希子さんはすでに2007年に亡くなっているため、法定相続人は長男一茂氏、長女有希さん、次女三奈さん、次男正興氏となります。この4人はメディア露出の多い一茂氏と三奈さん、プライベート重視の有希さんと正興氏という2つのグループに分かれ、お互いの関係はかなり複雑です。その主な原因は父茂雄氏と長男一茂氏との間に確執があり、親子の対話がほとんどなく絶縁状態に陥ったことによります。そのため先日行われた葬儀の喪主も、茂雄氏の信頼が厚かった次女三奈さんが務めました。
4人の子供による法定相続での分割割合は、各相続人25%ずつとなります。ただし以前に一茂氏は相続を放棄するような話をしていたことがあり、それが正式な手続きとして認められた場合は残り3人で分割することになります。しかし長嶋家のように不動産が多いと、どの遺産を誰がどのように相続するかという分割問題は決して簡単ではありません。また現在「オフィスエヌ」が管理している肖像権や商標権の問題も、相続人の間でどのように処理するかについて十分な協議が必要でしょう。
こうした長嶋家の複雑な相続問題において決定的に重要なのは、茂雄氏が遺言書を残しているかどうかという点です。それがあればその内容に基づいて比較的スムーズな相続が可能となるでしょう。しかし残念ながら確かな情報が伝わっておらず、その有無は今のところ不明です。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年6月】
相続税はどれくらい?
相続税については以前も取り上げたことがありますが、多くの人の関心事と思われますのでまた取り上げてみます。
古くは日露戦争の戦費調達のため導入されたと言われる相続税ですが、その後時代とともに目的が変わってきました。そもそも相続財産は、労働による対価ではなく「不労所得」のようなものです。多くの人は働くことでお金を得ており、そのお金には所得税がかかります。となると「不労所得」に税の負担がなければ、不公平感が生じてしまいます。それを解消するための手段が相続税というわけです。
この不公平感の解消と共に、相続税には次の二つの目的があるとされます。一つは富裕者の財産に課税することでそれを減らし、財産が少ない人に再分配して格差を縮小することです。あと一つは生前に非課税所得や少額贈与などさまざまな理由で軽減(節税)された財産を、相続時において課税し精算することです。
このような目的の相続税ですが、相続した場合に必ず課税されるわけではありません。相続した財産から借金や葬式費用を差し引いた残りの額が、一定額=「基礎控除額」を上回る時にだけ相続税がかかります。

この「基礎控除額」はバブル期に引き上げられましたが、その後見直されませんでした。そのため相続税がかかるのは被相続人のわずか4%程度だったため、平成25年度税制改正でそれを10%程度にまで広げると共に税率の見直しが行われました。現在の「基礎控除額」の計算式は次の通りです。
【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】
例えば法定相続人が配偶者と子ども2人の場合は【3,000万円+(600万円×3人)】で4,800万円となり、相続財産が4,800万円以下なら相続税はかかりません。
ただし配偶者の場合は、法定相続分または1億6千万円のいずれか多い方の金額まで税額控除があるため、それを超えなければ課税はありません。
相続税の税率は「基礎控除額」を超えた金額に応じて変わる累進課税で、1,000万円以下の10%から6億円超の55%まで少しずつ高くなります。
この税率を欧米など先進国と比べてみると、イギリスは一律40%、フランスは5%~45%、ドイツは7%~30%です。アメリカは遺産税と呼ばれ税率は18%~40%ですが、約6億円の基礎控除があるため大半の人はかかりません。日本がやや税率が高い気もしますが、正確な比較はなかなか難しいと言えます。
このような相続税がある国は44か国なのに対し、相続税がない(または廃止された)国は、香港、中国、シンガポール、マレーシア、タイ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、スウェーデン、ポルトガル、オーストリア、ノルウェーなど83か国にも上ります。世界的に見ると相続税のない国の方が多いのです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年5月】
相続したくない財産
最近ある不動産会社が相続したくない財産のアンケートを行い、そのランキング結果を発表しました。その上位5と、それぞれの主な理由を記してみます。
1位:不動産➡自分で住んだり使ったりしない、築年数が古く資産価値がない、など。
2位:お墓 ➡遠くにあるため掃除が大変、将来の管理や費用に限界がある、など。
3位:借金 ➡自分の借金ではないのになぜ返済しないといけないのか、など。
4位:骨董品➡価値がわからず処分に困る、売ってもあまりお金にならない、置くスペースがない、など。
5位:車 ➡名義変更手続きに手間がかかる、自分の車がある、興味がない、など。
これらを見ますと、それぞれきわめてもっともな理由から相続したくないと考えていることがわかります。1、2位の不動産やお墓は移動させにくく、管理が大変という共通点があります。また3位の借金は誰しも抱えたくないですし、4、5位の骨董品や車は個人の好みが関係するものなので扱いにくいという難点があります。
このように資産的な価値があって換金しやすい財産以外は相続したくない、という相続人の本音がうかがえるアンケート結果となっています。
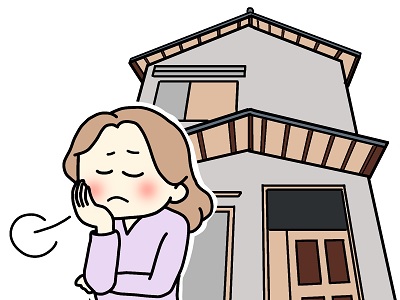
このような相続したくない財産がある場合、相続人が複数であればまず「遺産分割協議」において自分以外の人に相続してもらう方法が考えられます。自分は嫌でも他の人にとっては利用価値が高いことがあるからです。
「遺産分割協議」とは相続人同士で遺産をどのように分割するかを決める手続きのことで、協議を通じて特定の財産を誰が引き受けるかを決めることができます。
不動産の場合では、ある相続人が都市部の不動産を引き受け、別の相続人が田舎の不動産を引き受けるといった合意が成立することがあります。ただし「遺産分割協議」には相続人全員が同意しなければなりませんので、十分な話し合いが必要です。
次いで考えられるのは「相続放棄」ですが、法律的には遺産の一部だけ選んで残りを放棄することはできません。「借金」など債務だけを相続したくない場合は、遺産の全部を放棄する代わりに「限定承認」という手続きを利用することができます。
これは債務がプラスの遺産を超えるおそれがある場合の方法で、相続人は相続遺産の範囲内でのみ債務を負担します。これによりそれ以上の債務を支払う必要はなくなります。ただし「限定承認」には相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限がありますので、早めに当事務所のような相続の専門家に相談することをお勧めいたします。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年4月】
中小企業の事業承継
企業の経営者がその会社や事業を後継者に引き継ぐことを、事業承継と呼んでいます。日本ではこれまで、経営者の子供など家族や信頼できる部下を後継者とするのが一般的でした。
しかし近年は適切な人材が見つからないまま経営者が高齢化し、廃業や解散を迫られる中小企業が増えています。『中小企業白書』によれば、2025年度までに中小企業経営者の平均引退年齢である70歳を超える経営者は約245万人おり、うち約半数の127万人は後継者が未定とされます。
ある調査によれば、この後継者未定の中小企業の多くは廃業を予定していると回答しています。まさに大廃業時代の到来です。廃業を放置するとその影響により国内で約650万人の雇用が失われ、約22兆円のGDPの損失が見込まれると予想されています。
その廃業理由としては「当初から自分の代でやめようと思っていた」が38%と最も多く、次いで「親族に後継者が不在」が29%、「事業に将来性がない」が28%となっています。
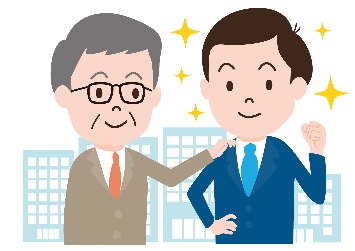
ただしこれらの企業のうち約3割は「同業他社よりもよい業績を上げている」と回答しており、さらに今後10年の業績見通しについて約4割が「少なくとも現状維持が可能」と回答しています。
この回答結果からは、企業として業績が良好な状態にもかかわらず、廃業を選択せざるをえない傾向があることがわかります。これではせっかく築き上げた企業の資産や人材をみすみす失うことになり、社会にとっても大きな損失と言えます。
こうした損失を防ごうと、近年は事業承継において社内以外の社外承継が注目されています。その対策としてオンラインでのM&Aマッチングサービス、公的機関である事業引継ぎ支援センター、さらには銀行、証券会社、保険会社など民間大手がM&A仲介事業に参入開始するなどしています。
「事業承継税制」も導入され、事業の後継者が取得した一部資産について贈与税や相続税の納付が猶予されたり、また「特例制度」で相続者が申告期限の翌日から5年間代表取締役を務めれば相続税を実質負担しなくてよいことになりました。
このように事業承継をめぐる環境は、近年大きく変化しつつあります。これによって中小企業の事業が、スムーズに次世代に引継がれることを期待したいものです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年3月】
神戸市の『樹林墓地』計画
お墓の問題については、本コラムでもこれまでたびたび取り上げています。
例えば2023年1月の「お墓の承継について考える」では、少子化や核家族化さらには寺院の檀家制度の形骸化などによりお墓の承継が難しくなっていること。そこで増えているのが「個別にお墓を持たない」という考え方で、そのために寺院や霊園の「永代供養墓への合祀」や「納骨堂」に納める方法、さらには樹木の下に埋葬する「樹木葬」や遺骨を海や山に撒く「散骨」などについてふれました。
また2024年10月には葬儀やお墓の形の変化として、家族葬の増加と共にお墓もかつての伝統的な和型石材から多様化しつつあり、断捨離して何も残さず自然に帰りたいとの気持から「樹木葬」や「海洋葬」「山葬」などの「散骨」といった方法を選ぶ人が増えていること。また「納骨堂」方式や、さらには1平方㍍以下の「小型墓」と呼ばれるものが増えていることなどを取り上げました。

こうした世の中の変化に合わせ、最近神戸市が新しく樹木の下に遺骨を共同で埋葬する『樹林墓地』を整備することを発表しました。市によりますと『樹林墓地』とは墓石などの代わりに樹木を植えその下に遺骨を共同で埋葬するものです。
市は近年の少子高齢化が進む中で墓地に対する意識が大きく変化しているとして、それに対応するため以前から新たな施設の整備を検討してきました。そしてこのたび久元市長が定例の記者会見において、この『樹林墓地』の構想と整備計画の概要を明らかにしました。
それによりますと、神戸市北区の森林公園内に約1200平方㍍の墓地を整備し、そこにおよそ1600体の遺骨を受け入れるということです。本年夏頃から工事を始め、来年(2025年度中)には完了させる見込みです。そのための整備費用として約7千万円程度を予定していて、新年度予算案にその経費を盛り込むことにしています。
市によると、自治体としてこのような『樹林墓地』を整備するのは全国の政令指定都市で初めてとのこと。市長は「亡くなった後にどのような埋葬を望むかという気持は、ここ10年ほどの間に急激に変化してきている。市として「樹林葬」の取り組みを新たにスタートさせたい」と述べています。
今後は他の自治体でも同じような取り組みが増えそうです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年2月】
国籍と夫婦別姓問題について
アメリカのトランプ大統領が就任早々、国籍の「出生地主義」を廃止する大統領令に署名しましたが、連邦地裁が一時的差し止めを命じたとのニュースが流れました。国籍は国家という共同体の構成員であることを示す資格のようなもので、相続においても重要な問題となります。
「出生地主義」とは誰でもそこで生まれただけでその国の国籍が得られるもので、これに対するものとしては親との血縁によって定める「血統主義」があります。ただしどちらかだけで決めるのではなく、もう一方も補完的に考慮して決めるのが一般的と言われます。
トランプ大統領は不法移民対策の一環として実施しようとしていますが、ちなみに「出生地主義」が多いのは北中南米の国々で、アメリカの他、カナダ、ブラジル、アルゼンチンなどです。アジアでは、今回のアメリカと同じようにバングラデシュからの不法移民に悩まされたインドは2004年にこれを変更しています。
日本は原則として「血統主義」で、フランスやドイツといったヨーロッパの先進国も以前は「出生地主義」を採用していましたが、いずれも二十世紀に入ってから「血統主義」に変更しています。

この「血統主義」は、国家というのは血縁や民族としてのつながりが基本であるとの考え方から生まれたもので、親子関係が重視されています。そしてこの「血統主義」には父母の国籍が関係しています。
父母の国籍が同じであれば問題はないのですが、両方の国籍が異なる場合に、父の国籍が自国であればその子にも認められるのを「父系優先血統主義」と言います。また父母どちらかの国籍が自国であれば、その子にも認められるのを「父母両系血統主義」と言います。
ですから「父系優先血統主義」の国においては、母の国籍だけ自国の場合にはその子が認められるかどうかはそう簡単ではありません。
これを聞くと、最近日本で大きな問題になっている「選択的夫婦別姓」を思い出します。それは単に夫婦の姓をどうするかという「旧姓の通称使用拡大」などに止まらず、その子供の姓をどうするかが問題の根本となっています。すなわち父母(夫婦)とその子供の関係をどうするかという問題です。その意味では、国籍の話とよく似た側面を持っています。
これについては血縁や共同体という国家の伝統をどう守るかというナショナリズムの問題が根底にあるだけに、なかなかすっきりと解決するのは難しいと言えます。すでに30年近く検討されているわけですが、はたして近いうちに明確な方向を打ち出せるのでしょうか。それともまた先送りとなるのか、注目されるところです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2025年1月】
『エンディングノート』あれこれ
新年おめでとうございます。今年こそ災害のない一年でありますように。
さて今月は、終活とも関連する『エンディングノート』の紹介をしてみたいと思います。言うまでもなくもしもの時に備えて、残された家族に迷惑がかからないよう大切なことがらを書き記しておくノートのことです。しかしいざ書こうと思っても、何からどう書けば良いか悩んでしまう方が多いのではないでしょうか。こうした声に応え、最近はわかりやすく書きやすい『エンディングノート』が多数販売されています。
一般社団法人終活協議会による『はじめの一冊 オリジナルエンディングノート』は、表紙にエンディングノートとの記載は特にないものの、自分自身のことやパソコン、スマホ、さらには各種資産、生命保険や葬儀、お墓、ペット、介護、医療、連絡先といった大切な情報をもれなく記述できるようになっています。このため情報整理用としても大いに役立つノートです。
気負うことなく気軽に書けるという点が評価されていて、本格的な終活の前に自分の情報を整理するものとして格好のツールと言えます。
多くの終活セミナーの受講者の声をもとに、すらすら書きやすいものを目指したという『一番わかりやすいエンディングノート』は、行政書士法人事務所代表の東優(ひがしまさる)氏著作のものです。
書き込みやすいノート仕様となっていて、終活の流れに沿って順番に書き込んでいくとそのまま完成するのが特徴です。暗証番号などの重要情報を保護する「マル秘カード」や「スクラッチシール」も付いています。さらに40年ぶりの令和の改正相続法に対応している点も安心と言えます。

文具メーカーのコクヨからはこだわり仕様の「エンディングノート もしもの時に役立つノート」が販売されています。これは日々の生活の備忘録としても役立つ、大切な情報を一冊にまとめられるノートです。
相続で大変なのは、何がどれだけあるかを調べることと言われます。銀行口座はいくつ、クレジットカードは何枚、現金以外の資産や借入金はどれだけ、口座引落しはないか、サブスクには入っているのか、等々については残された人が特に苦労します。そのような情報をきちんと整理しておける他、日常生活での財布やクレジットカード紛失など様々な「もしもの時」に役立ちます。CDや写真なども入れられるディスクケース付きです。
文響社の「生前整理ノート」は全く新しいタイプのエンディングノートで、自分に関するさまざまなことを元気なうちに書き込めるようになっています。
具体的には、預貯金、株式、保険、不動産、貴金属、借入金などの資産内容や、金融機関の口座番号と暗証番号、不動産権利書や遺言書などの保管場所、サブスク契約、パソコンやスマホのパスワード、医療介護や葬儀、お墓の希望など、あらゆる情報を書き込むことができます。
さらに「書き込み家系図」「日本と世界の書き込みマップ」や「入院・介護時の備え書き込み帳」「やり残したこと実践計画」など、多くの新しい内容が盛り込まれています。
他にも各種のものが多数販売されていますが、いずれも高齢者の終活用としてだけでなく、若い方が日々の生活の備忘録としてこれらのノートを活用するのも有力な方法と思われます。