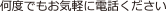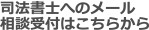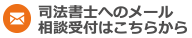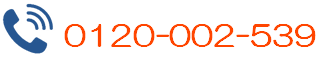相続よもやま話〈2023年〉
~毎月1回お届けする相続に関する楽しいイラスト付きエッセイ風コラム~
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
目次
(2023年12月) 相続登記をお急ぎください
(2023年11月) 空き家の有効活用を考える
(2023年10月) 不要な空き地をなくすには
(2023年9月) 福原愛さんの長男と共同親権
(2023年8月) 任意後見制度の目的としくみ
(2023年7月) 家族信託の目的としくみ
(2023年6月) 認知症に備えるために
(2023年5月) 子育てのセーフティネット
(2023年4月) 特別な「寄与」と「受益」の話
(2023年3月) 離婚の増加と共同親権について
(2023年2月) 戸籍をたどる方法とは
(2023年1月) お墓の承継について考える
(2025年当月~1月) 目次
(2024年12月~1月) 目次
(2022年12月~1月) 目次
(2021年12月~1月) 目次
(2020年12月~1月) 目次
(2019年12月~1月) 目次
(2018年12月~1月) 目次
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年12月】
相続登記をお急ぎください
10月は空き地、11月は空き家の問題を取り上げました。それに関連して今月は相続登記の話をさせて頂きます。相続登記とは相続によって不動産を取得した場合に、所有者として名義の変更をする手続きのことで、これによって第三者に対し自らの権利を明示することができます。
空き地や空き家の問題で述べたように、わが国においては所有者不明あるいは相続したにもかかわらず名義変更されていない土地や建物がかなりの数に上っており、そのことがこの問題を複雑化させている大きな要因の一つです。
そのため相続登記を促進させようと2021年2月の法制審議会で不動産登記法改正の要綱案が決定され、さらに4月に法案が可決成立し、それがいよいよ来年4月1日からの施行となります。
一般的に相続が発生した場合、主な手続きの流れとその期限の目安については次のようになっています。
まず被相続人が亡くなって7日以内に死亡届を自治体に提出し、葬儀などを済ませた後、3ヶ月以内に遺言書の有無や相続人、遺産などの調査を行い、相続放棄する場合はその手続きをします。
その後、相続人が複数の場合は必要に応じて遺産分割協議を実施し、遺産の名義変更を行うことになりますので、この段階で土地や建物など不動産については相続登記をします。これらの手続きは、相続税の申告が必要な場合はその申告と納付の期限が10ヶ月以内となっていますので、それに合わせて行うことが望ましいと言えます。

相続税の申告が必要ない場合でも、相続登記は不動産登記法の改正により相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に法務局に申請することが義務となります。正当な理由がないのにこの登記申請をしなかった場合は、最大で10万円の過料が科されます。
また住所変更した場合も不動産登記が義務化されており、こちらも2年以内に正当な理由がなく手続きしなければ5万円以下の過料が科されますので注意が必要です。
今回の法改正以前から所有している不動産の相続登記や住所変更等の登記が完了していないものについても、同じように義務化されるためできるだけ早く登記申請を行う必要があります。
なおこれらの不動産の相続や遺産分割協議などを行う場合は、まずその相続財産としての評価額がどれくらいなのかを知ることが前提となります。これについては不動産の相続税評価額は、土地の場合は実勢価格の8割程度が基準とされていて、その計算方法は「路線価方式」(路線価×面積)や「倍率方式」(路線価がついていない場合で固定資産税評価額×倍率)が一般的です。また建物の場合は「固定資産税評価額」をそのまま適用します。
ただしこれらは一つの目安であって厳密なものではないため、場合によっては相続人同士の話し合いが必要になることもあります。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年11月】
空き家の有効活用を考える
先月の空き地に引き続き、今月は空き家の問題を考えてみたいと思います。これについては相続登記の義務化と関連して、一昨年の3月にも取り上げたことがあります。
少子高齢化の急速な進展とともにわが国の空き家は年々増加し、ある予測では今年は1,293万戸、空き家率は19.4%に達するとも言われています。約2割ですから5軒に1軒です。増加率は年々鈍化しているものの、やはり大変な数であることは間違いありません。空き地と同様に、景観や防犯上さらには衛生面など様々な問題を抱えていると言えます。
中でも最近目に付くのは、高齢者が亡くなられて大量の家具や物品が遺品として放置されたままの空き家です。
一人暮らしや施設に入居したまま亡くなる高齢者が増えると、長年にわたり家具や物品が放りっぱなしとなり、また不用品やゴミも多くなります。そうした状態の空き家を相続した場合、その遺品や不用品の多さに困惑してしまうといったことも起こります。
こうした時にはその処分方法を考えることも大事ですが、その前にまず空き家自体をどうするかを決めるのが先決と言えます。特に相続人が複数の場合はよく話し合って、売却という選択肢なども含め、慎重に検討する必要があります。すなわち空き家を建物として残し再利用するのか、あるいは全て取り壊して更地にするのかなどです。
利用目的によっては固定資産税など税制の問題も関係しますので、十分な比較検討が望まれます。
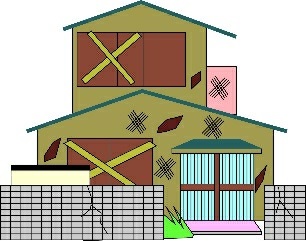
建物を残す場合は、古い家具は再利用するといったことも考えられます。レトロな雰囲気を持つ家具は、若い人にとっては大いに利用価値がありそうです。屋根や柱、壁なども築年数による老朽化の度合いを見究めて補修すれば、まだ十分使用に耐えるかもしれません。
そんな中で最近注目されているのが、相続人が所有者のまま空き家をDIY賃貸住宅とする方法です。これは不動産業者が仲介して行なうもので、空き家をDIY賃貸住宅として貸出し、入居者が自分のライフスタイルに合わせてDIYリフォームを行ないます。屋根や柱などは保持したまま取り壊す必要がなく、所有者にとっても賃借人にとってもメリットのある方法と言えます。
このようにあらかじめ建物をどうするか決めた上で、家具や物品をよく確認し、その処理方法を検討するのが良いと思われます。そのまま再利用するのか、他の相続人が引き取るのか、あるいは誰かに売却するのか捨てるのかなどを決めて行きます。業者に処理を依頼する場合は、家具や物品数が多いとかなりの費用が発生することもありますので注意が必要です。
いずれにしても建物や家具などの再利用が一つの大きな流れとして定着し、多くの空き家が有効に活用されることを願うしだいです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年10月】
不要な空き地をなくすには
近年、空き家や空き地の問題が大きくクローズアップされています。これには核家族化や少子高齢化、さらには相続や登記などの問題が複合的に関係しているため、その解決は容易ではないように思われます。今月はその中で、まず空き地の問題を取り上げてみたいと思います。
一口に空き地と言っても、そもそも所有者が不明というのもあれば、所有者は明確でも何らかの理由により利用されていないというのもあります。そして私たちの普通の感覚では、所有者は明確だが単に利用されていないだけというのが多いように思われますが、そうとばかりも言えないようです。
以前の国交省による所有者不明土地の実態調査によれば、全国で所有者が不明の土地は20.3%もあり、面積では410万haにも及ぶとのことです。ちなみに九州の面積が368万haですから、それより広い土地が所有者不明ということになります。
これには都市部だけではなく農山村部も含まれますから、それほど驚くような話ではないのかもしれません。しかし日本の国土のうち2割余りが所有者不明というのは、土地という資源の有効活用や国土保全の観点からも決して望ましいこととは言えないでしょう。当然ながら所有者不明のままでは何をすることもできないため、国として解決のための抜本的な方策が求められるところです。

一方で、所有者は明確でも全く利用されていない土地があります。これについては今年4月から「相続土地国庫帰属制度」というのが始まりました。これは簡単に言えば相続した不要な土地を、国が引き取る制度のことです。
利用されていない土地の相続が重なっていくと、相続人の関係もしだいに複雑になり、きちんとした登記や売却、相続放棄などが簡単にできなくなります。そしていつしか所有者不明となり、土地は荒れていき管理も困難になります。そうしたことを防ぐために国が引き取る制度ですから便利とも言えますが、注意すべきいくつかの条件があります。
まず申請をするには、建物がない更地であることが必要です。空き家があれば自己負担で取り壊しや滅失登記を行います。また土地の利用者がおらず、担保権などが設定されていないことや、境界線が明確であることなどの条件が設けられています。(法務省のホームページに18項目掲載されています)
申請は相続人が行い、共有地の場合は全員の合意が必要です。合意が得られなかったり、登記をしておらず所有権の確認が困難な場合は申請は認められません。
このような条件を満たしている場合でも、国に引き取ってもらうには土地一筆当たり1万4千円の審査手数料や原則20万円(面積に応じ一定額が加算される場合もある)の負担金が発生する点に注意が必要です。
このように見てくると、新たな所有者不明の土地をなくすために一定の効果はありそうですが、引き続きこの制度を利用しやすくするためにはなお一層の改善が求められると言えます。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年9月】
福原愛さんの長男と共同親権
最近、元卓球選手の福原愛さんが、離婚した同じく台湾の元卓球選手江宏傑氏との間にできた二人の子供のうち長男を日本に連れ帰り、江氏と争いになっていることがニュースなどで報じられています。こうした親権に関することについては、昨年12月「親権と子供の連れ去り問題」と本年3月「離婚の増加と共同親権について」で、主に共同親権の話として2回取り上げています。
国際結婚をして離婚した女性が、子供を日本に連れ帰って問題になるケースはこれまでもありました。その原因は日本と諸外国の間で、離婚後の子供の親権に関する考え方に大きな違いがあることによります。日本では両親いずれかの単独親権となるのに対し、外国では共同親権のままが多いのです。日本では子供と暮らす親に単独親権が認められることが多いので連れ帰ってしまいがちですが、ヨーロッパではハーグ条約により子供の連れ去りがあった場合は原則として元の居住国にすぐ返還することが定められています。
今回の福原さんと江氏の場合は台湾の規定でどちらも子供の共同親権者なので、親権をめぐる争いではありません。お互いに子供とは平等に接することができるため、昨年の夏休み中は愛さんが二人の子供を預かる約束になっていたようです。しかしなぜか空港で江氏が突然反対して騒ぎとなり、愛さんは長男しか連れ帰れなかったとの報道もあります。
そのあたりの真相は不明ですが、江氏は弁護士を通じて訴えを起こし、7月に東京家庭裁判所から福原さんに長男を引き渡すよう「保全命令」が出されました。その後も双方の弁護士が会見や声明を出すなどして事態は沈静化することなく、日台双方でさまざまな意見が飛び交っているようです。

離婚後の共同親権については、わが国ではただ今法制審議会で年内に大筋の案がまとまるよう検討中です。そのおおよその骨子は次のようになっています。
・両親の協議により、離婚後は単独親権か共同親権のいずれかを選択できる。意見が対立した時は家庭裁判所が子供の利益を考えて裁定する。
・共同親権中は両親は共同で親権を行使するが、子供の身の回りの世話(監護)や教育に関しては両親のいずれかが単独でも決定できる。両親の意見が割れた場合は、家裁が親権を行使する親を選ぶ。
・両親の力関係によって一方が共同親権を強いられたり、共同親権によって離婚後も家庭内暴力(DV)や虐待が継続しないように、不適切な共同親権は排除できるようにする。
・「暴行や有害な言動がある」「共同親権によって円滑な親権行使が難しくなった」といった特別な事情があれば、子供や親族の求めで家裁が親権者を変更できるようにする。
このように、わが国でもようやく離婚後に共同親権が認められる方向で案がまとまりそうです。共同親権だからといって福原さんのようなトラブルが起こらないとは限りませんが、それでも離婚後の子供をめぐる問題に関して一歩前進であることは間違いないと言えます。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年8月】
任意後見制度の目的としくみ
6月のコラムでわが国の認知症者が2025年には約700万人に達する見込みで、それに備えるため「家族信託」や「任意後見制度」があること、そして先月は「家族信託」についてご説明しました。今月は引き続き「任意後見制度」を取り上げます。
「任意後見制度」は認知症などの病気や障害等により本人の判断能力が十分でない場合に備え、家族や友人など信頼できる人を後見人に選定して、生活や財産の管理を「任意後見契約」を結んで引き受けてもらう制度です。 後見人の選定は本人の意向や生活スタイルに合わせ慎重に行う必要がありますが、専門家や公的機関に依頼することもできます。
似た言葉として「成年後見制度」がありますが、「任意後見制度」はこの「成年後見制度」のうちの一つで、「法定後見制度」に対して使われる言葉です。「任意後見制度」は判断能力が不十分になる前に自分の意思で契約書を作成して行うのに対し、「法定後見制度」は本人の判断能力が不十分になった後で、周囲の方などの申し立てにより家庭裁判所が後見人を選任するものです。
このように「任意後見制度」はあくまでも本人が後見人との合意によって「任意後見契約」を結び、後見人に依頼する行為の権限や責任範囲、報酬などを具体的に定めるものです。そのメリットとしては本人の意思が尊重され、自立した生活が続けられることや、その生活スタイルに合わせた柔軟なサポートができることなどが上げられます。

その手順としては、まず後見人である「任意後見受任者」を決めます。資格は特に必要なく、家族や親戚、友人などに加え、私たち司法書士などの専門家や法人でも可能です。また複数選ぶこともできます。ただし未成年者はなれません。
次に後見人との間で「任意後見契約」の具体的な内容を決めます。後見人に何を依頼するかは、当事者同士で自由に決めることができます。財産管理に関すること、あるいは医療介護サービスに関することなどです。たとえば入所希望の介護施設や受診したい医療機関への事務手続き、その他生活に関する希望事項などを契約書に記載するとよいでしょう。
「任意後見契約」は公正証書によって行うことが定められています。本人の意思をしっかり確認し、契約内容が法律的に確かなものであるように、公証人が作成します。公証人からその場で内容について適切なアドバイスをもらうこともできます。
高齢化が進む中で「任意後見制度」の重要性はますます高まっており、本人の意思を尊重した適切なサポート体制が欠かせません。すべての高齢者や障害者が十分な支援を受けられるように、今後のさらなる制度の充実と運用方法の改善が求められています。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年7月】
家族信託の目的としくみ
最近、家族信託という言葉をよく目にするようになりました。これは先月取り上げた認知症への備えの一つとして、自分の財産を介護費用などに使えるように、家族など信頼できる人にその管理を任せる制度です。平成18年に信託法が改正され、当事者の意向に沿って自由に設計できるようになり注目されています。これによって認知症になっても、あらかじめ思っていた通りに財産を活用することができます。
この家族信託は、委託者(財産を委託する人)、受託者(委託された財産を管理運用する人)、受益者(それによって利益を得る人)の三者による契約で成立します。その名称から、受託者は家族(または親族)だけと思われがちですが、財産を信頼して預けられる人であれば親族でなくても受託者にすることができます。
また委託者と受益者は同一人物のことが多いのですが、それ以外の人を受益者にすることもできます。たとえば未成年の子供や特定の家族への経済的支援のために利用することもあります。生前相続対策として受益者に毎年少しずつ財産を贈与したり、遺言書ではできない承継順位指定や二次相続対策といったことも可能です。ただし委託者と受益者が異なる場合は、贈与税などの問題もありますので注意が必要です。
家族信託では、まずどんな目的で誰にどの財産を委託するかを決めることが大切です。この点があいまいだと、後でトラブルの原因になります。家族などでそれぞれの意思を確認するためよく話し合いたいものです。
財産としては現金・預金、不動産(賃貸物件含む)、有価証券、貴金属、骨董品、自動車等がありますが、金額に特に制限はありません。しかしあまりに高額になると受託者に大きな負担となりますので、適切な金額の設定が望まれます。
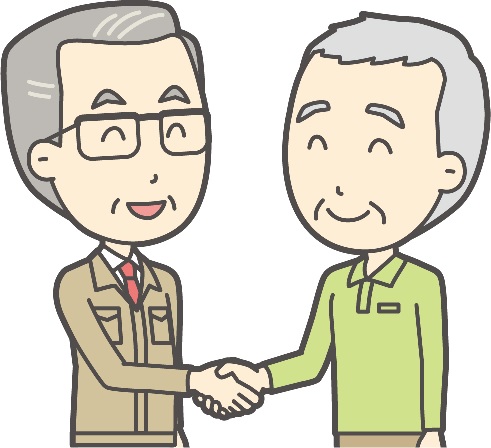
それらが決まったら、契約書を作成します。制度自体がまだそれほど普及していないため書式も十分に確立されていませんので、専門家の力を借りるのも有力と思われます。
契約書をより確かなものにするため、公正証書として作成する方法もあります。最寄りの公証役場で契約書を作成し、委託者と受託者双方の印鑑を押して、手続き完了となります。公証役場で保管されるので、紛失リスクを回避できる利点もあります。
信託財産は、受託者自身の財産と区分して管理しなければなりません。そのため専用の口座である信託口(しんたくぐち)口座で管理します。信託口口座を開設できる金融機関は限られていますので、事前に確認しておきましょう。金融機関によっては公正証書が求められますので、それらの必要書類を提出し信託口口座を開設します。
また財産の中で不動産などは委託者から受託者への名義変更が必要となりますが、単なる「所有権移転登記」ではなく「信託登記」として名義変更し、委託者からの信託財産であることを明記します。
このように家族信託は今後ますます増える認知症に備えた財産管理の有力な方法ですので、高齢者の方々はその活用を検討されてはいかがでしょうか。
その手続きにおいては、信託契約や相続の専門知識が必要なため、やはり法律職である私たち司法書士などの専門家へ依頼するのが一般的と言えます。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年6月】
認知症に備えるために
わが国は今、人口が減少する一方で高齢化が急速に進んでいます。総務省の発表では2022年10月時点で65歳以上の高齢化率は29%に達しており、2050年には37%になると予測されています。それと並行して認知症の人が増え、2年後の2025年には約700万人と65歳以上の5人に1人が認知症になると見込まれています。
確かに最近はご近所さんなどを見ても、そうした方が決して珍しくはないことを実感するようになりました。こうした認知症になると、当然ながらさまざまな困った問題が発生します。記憶が曖昧になり物が覚えられなくなったり、簡単な計算や判断ができなくなったりします。
その結果いろいろなトラブルや詐欺などに巻き込まれやすくなります。生活資金の面でも、預貯金口座の解約や引き出しができなかったり、不動産や証券の売買、保険の解約や受取り請求ができなくなります。また介護費用を家族が負担する場合は、生活が圧迫されることになります。
さらに相続においても遺言書の効力をめぐって争いが起きたり、さまざまな相続手続きができなくなります。これは被相続人だけでなく相続人が認知症となった場合も、遺産分割協議ができなくなるなど同じ問題が起こります。
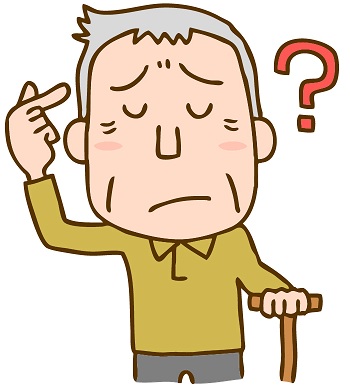
ところで法律的な行為(契約)において、認知症はどのように判断されることになるのでしょうか。一般的に契約は双方の意思の合致によって成立しますが、それを有効に締結するには「意思能力」と「行為能力」の2つが必要とされます。「意思能力」はその行為の結果を判断できる能力で、これを欠く人の契約は無効とされます。認知症の人は、民法上「意思能力」のない者として扱われます。
また「行為能力」は単独で有効な契約を行なうために必要な能力で、その能力に欠けた人の契約は取り消すことができます。この「行為能力」が制限された人は「制限行為能力者」とされ、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人などがこれにあたります。
その能力を補う者として成年後見人や保佐人、補助人等が定められています。すでに認知症となった場合は、こうした人にサポートしてもらうことになります。
一方で認知症になる前であれば、「任意後見制度」や「家族信託」の活用といった方法があります。「任意後見制度」とは将来自分の判断能力が不十分になった時に備えて、後見人を依頼し、その内容を契約(公正証書)で決めておく制度です。
また「家族信託」も認知症になった場合に備え、ご自身の財産の管理を親族など信頼できる人に任せておく制度です。
元気なうちに将来のことを家族などで話し合い、必要な手続きをしておくことをぜひお勧めいたします。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年5月】
子育てのセーフティネット
相続と直接の関連はないのですが、現在わが国は前列のない少子高齢化の時代を迎えています。国交省の発表によれば2050年の人口予測は9,515万人と、今より約3,300万人(約25%)も減少します。しかも65歳以上の高齢者は1,200万人増加して3,764万人で、その比率は20%から40%に増え、逆に15~64歳の生産年齢人口は3,500万人減少して4,930万人で比率は約50%ほど。ですから一人の労働者がほぼ一人の高齢者を支えて行かなければなりません。
27年後というのは例えば38才の人がちょうど65歳の高齢者になる頃で、そんなに遠い将来の話ではなくすぐそこの現実と言えます。これらはすべて生れて来る子供が少ないことに起因しています。
さすがに政府がようやく異次元の少子化対策を打ち出しましたが、あまりに遅過ぎますしうまく行く保証もありません。バブル後の90年代頃からもっと真剣に取り組む必要があったのですが、30年以上先延ばしされ今に至っています。わが国は安心して子供を生める社会になっておらず、結婚したり子供を生むことが将来の大きなリスクになっているのが現状です。
言い換えると私たちの社会が目先の生活だけを重視して、この30年余り子供のことを大事に考えて来なかったツケがいま回って来ているのだと言えましょう。

子供を安心して生むためには、結婚しているいないに関わらず経済的困窮など様々な理由により親の子育てが困難になった時に、社会がその受け皿としてセーフティネットを用意しておくことが重要でしょう。わが国ではそのため、児童養護施設の他に里親や「ファミリーホーム」の制度があります。
親と暮らせない子供は現在全国で約4万2000人いると言われますが、里親または「ファミリーホーム」に委託されている子供の割合は全国平均で約22.8%(令和2年度)で、就学前目標の75%以上や学童期以降目標の50%以上にはまったく達していません。
里親は実親の元にいられない子供を育てるもので、養子縁組と違って親子関係(親権)はありません。2016年の児童福祉法改正により家庭的な環境での養育を重視する方針が示されましたが、里親への委託は思うように進んでいないのが実状です。
また「ファミリーホーム」は厚労省が定めた「小規模住居型児童養育事業」を行うもので、経験豊かな養育者が家庭で5~6人の子供を預かり、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を付与することを目的とする制度です。令和3年時点で全国に427ヶ所あり、委託児童数は1,688人で、将来的には全国1,000か所を目標としています。
このような里親や「ファミリーホーム」を活用して子育てを側面から支え、少子化対策の一つとして大いに役立ててほしいものです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年4月】
特別な「寄与」と「受益」の話
相続に関する言葉は何かと難しいものが多いのですが、「特別寄与」と「特別受益」などもその一つでしょう。どちらも同じように「特別」が付いていますが、「寄与」と「受益」は正反対の言葉なので、意味もあべこべです。この二つをまとめて覚えておくと、わかりやすいかもしれません。
まず前者の「特別寄与」については、以前にも一度ふれたことがあります。簡単におさらいしますと、相続において相続人以外で被相続人の生活や財産の維持などに特別な「寄与」のあった人に、その分を金額に換算し「特別寄与料」として認めてあげる制度です。
ここで注意が必要なのは、相続人以外という点です。一般的に親が亡くなった場合に子供は相続人となりますが、その配偶者は親族であっても相続人ではないので、遺産を受け取る権利はありません。ですから例えば子供の配偶者が一生懸命に介護をしていても、何も得られないことになります。
近年高齢者の介護は大きな社会問題でもあり、こうしたケースで相続人ではないという理由で何も見返りがないのはやはり問題でしょう。そこで「特別寄与料」として、介護に費やした労務や時間に対し相当する金額を請求できるようになりました。ただし金額をどう計算するかについてはまだ明確な基準がありません。
一般的な考え方として介護職員の時間給に介護に費やした時間を掛けるなどが検討されているようですが、こうしたことが予想される方はあらかじめ介護日誌などの記録を残しておくことをおすすめいたします。もし金額について相続人との間で合意できない場合は家庭裁判所に申し立てをすることができますが、それを避けるためにはその非相続人の尽力に対して遺言で「特別寄与料」を言及しておくのが望ましいでしょう。
なお相続人が被相続人の介護を行ったり事業を手伝うなどしている場合は「寄与分」というものが定められており、これは遺産分割の際に考慮することになっています。

後者の「特別受益」とは、逆に相続人が被相続人から特別に遺贈された財産や、婚姻・養子縁組あるいは生計のために受けた贈与などのことを言います。
遺贈は、財産を贈与すると遺言書に書かれている場合です。また婚姻・養子縁組のための贈与はその持参金や支度金などで、結納金や結婚式の費用は該当しません。生計のための贈与は事業資金の援助や住宅購入資金などで、少額の生活費援助などは該当しません。
相続においては、この「特別受益」の持ち戻しというのがあります。相続人の中で被相続人から遺贈や贈与を受けた人がいる場合、同じように相続すると不公平になるため、贈与の一部を「特別受益」として法定相続分から差し引くというものです。
ただし「特別受益」の持ち戻しは、被相続人の意思で免除することも可能とされています。また法定相続人以外の者に対する遺贈・贈与は、「特別受益」の対象とはなりません。
「特別受益」は相続分の計算はもちろんですが、法定相続人の遺留分の計算にも影響します。ただし現行法では「特別受益」に含まれる生前贈与は「10年以内」のものという制限が設けられています。
相続分の計算についてはこの期間制限がなく、過去にさかのぼって「特別受益」の対象となります。なお受取人が指定されている生命保険金は、受取人固有の財産として相続財産に含まれないため原則的に「特別受益」には該当しません。
この「特別受益」は遺産分割や遺留分減殺請求において主張していくもので、それだけを単独で主張するものではありません。相続人が遺産分割協議の中で相手方は贈与などの「特別受益」があるため自分の受取分はもっと多いとか、遺留分減殺請求の中で相手方の「特別受益」から見て遺留分はないといった主張をすることになります。
今回は相続における「特別寄与」と「特別受益」という相反する二つの言葉について取り上げましたが、ご理解いただけましたでしょうか。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年3月】
離婚の増加と共同親権について
先日夜のNHK『クローズアップ現代』という番組で、離婚後の子育てに関する議論が国の法制審議会で行われていることを取り上げていました。そして離婚家庭の父母や子供たちの声、さらにオーストラリアの例を取材しながら子供の幸せにとって何が最善なのかを話し合っていました。
わが国の昨年の離婚件数は約20万8千件で、前年の約18万4千件に比べ2万件以上増えています。最近の婚姻件数は約60万件ほどなので、よく言われることですがおよそ3組に1組が離婚していることになります。離婚時に未成年の子供がいるかどうかは別として、単純に子供が1人いたと仮定しても毎年およそ20万人の子供に親権問題が発生していることになります。
この親権については本コラムでも昨年12月『親権と子供の連れ去り問題』というタイトルで取り上げています。これは主に国際結婚をして離婚した日本女性が、相手の承諾なしに子供を連れ帰って問題になるケースを話題にしたものです。
そこでも書きましたが、日本では離婚した場合は父母いずれかの単独親権となりますが、欧米など多くの国では離婚しても引き続き父母の共同親権が維持されるのが普通です。その制度や考え方の違いが、子供の連れ去り問題を生む一つの大きな要因となっています。

『クローズアップ現代』の番組で桑子真帆キャスターが語るところによりますと、法制審議会では中間試案として現在次の4つの方向でそれぞれのメリット・デメリットの比較などさまざまな検討を行っていると言います。
1.現在の単独親権を維持する
2.原則として共同親権とする
3.原則として単独親権とする
4.原則を設けず個別判断とする
共同親権のメリットとしては、離婚時に親権争いが起きないこと、離婚後も子供が父母と交流ができ養育費の不払いなどが少ないこと、教育について父母と子供が一緒に話し合えることなどがあります。しかし一方では、父母の間で意見の相違があると揉めてしまい、子供がその板挟みになって苦しむなどのデメリットもあります。
オーストラリアでは離婚後も両親が子育てに関わるという考え方が浸透していて、国をあげて共同親権に取り組んできました。しかし最近この共同親権のデメリットが問題となり、一部その見直しの動きが出ているとのことです。このように単独親権と共同親権のどちらが制度として優れているのかは、それぞれの国の事情や文化の違いなどもあってはっきりとは言い切れない部分があります。
その意味ではいずれかに限定するのではなく、両方の良い部分を取り入れながら柔軟に対応して行くという考え方もあります。法制審議会においても子供の幸せにとって何が大切かという視点から十分な検討を重ね、ぜひ世界に誇れるようなわが国の親権制度を作り上げてほしいものです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年2月】
戸籍をたどる方法とは
先月はお墓の承継について考えてみました。それは先祖代々のお墓という、家や家族のあり方の問題と密接に絡んでいます。そしてこの家や家族の問題と深く関係しているのが戸籍という制度です。
戸籍については昨年4月に「戸籍とは何のためにある?」でも取り上げました。それは簡単に言えば「国民一人一人を出生や婚姻関係などによって家族単位で登録する制度」のことで、私たちの法的な身分関係を示すものとして、パスポート発行や相続手続きなどに利用されています。
この戸籍は、婚姻や分籍(現在の戸籍から抜けて単独の戸籍を作ること)などがあれば新戸籍が作成されます。ですから一人の人間の戸籍は一つだけでなく、いくつにもまたがって連続していることが多いのです。これが戸籍制度を複雑にしている理由とも言えます。
そしてそれらは同じ本籍地にあるとは限らず、必要な場合はそれぞれの戸籍の本籍地である市区町村に請求することになります。相続手続きにおいてはしばしばこの問題が起こります。
一昨年9月に、本コラムで経済評論家の森永卓郎さんが亡くなった父の戸籍謄本を取り寄せるためにどれだけ苦労したかを「二度としたくない大変な作業」としてご紹介しました。父が生まれてから亡くなるまでのすべての居住地で、それらを集める必要があったのです。
しかし父は転勤が多く、あちこちに住所を変えていました。すべて郵送でも可能ではあったのですが日数がかかってしまうため、結局は自分で足を運んだとのことでした。

このように戸籍をたどることができるのは、戸籍には必ず入籍日とその一つ前の従前戸籍が記載されているからで、必要な場合はまず死亡時の本籍地で請求し、そこから順にさかのぼって取得して行きます。
また戸籍には「附票」というものがあります。これは本籍地の市区町村において原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記録されています。それを住民基本台帳と照らして閲覧すれば、転居の履歴が判明します。それによって連続した戸籍をたどることができるというしくみです。
相続手続きにおいて被相続人の戸籍をたどるのは、その配偶者や子供の有無などを確認し、誰が相続人なのかを確定させるためのものです。配偶者や子供がいない場合は、父母や兄弟姉妹の戸籍を調べる必要があることもあります。
また被相続人が亡くなった時に凍結された銀行口座を解除する手続きにおいても、必要書類の一つとしてその出生から死亡までの戸籍謄本を求められます。
これらの作業は思った以上に大変ですが、誰かがそれを行わなければなりません。私たち専門の司法書士に依頼するのも一つの有力な方法ですので、どうぞご遠慮なくご相談ください。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【2023年1月】
お墓の承継について考える
令和5年を迎えました。長かった新型コロナも、中国を除いてはようやく収束に向かう兆しが見えてきたようです。
さて相続というとまずは財産や相続人のことを考えるのが普通で、特にお墓や仏壇などを意識する方は少ないと思います。
以前の『祭祀やお墓に関する話』で、これらは相続財産には含まれず、民法で「祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する」と定められていて、それにはかつての「家」制度が関係していることを書きました。
古来より私たち日本人はお彼岸やお盆に先祖のお墓参りをし、それが家族をつなぐ絆にもなっていました。しかし今や大家族の時代は過ぎ去り、少子化や核家族化が急速に進んでこうした慣習は昔ほどには行われなくなっています。
さらに寺院の檀家制度がしだいに形骸化する中で、都市部と農村部のいずれにおいても「家」を守るという文化は失われつつあります。その結果として祖先の祭祀を行う者がいなくなり、多くのお墓で承継者が不在となって無縁墓になるケーが増えています。これは全国各地で空き家が増加しているのと同じ問題と言えます。
こうしたことから、最近は無縁墓とならないようあらかじめ「墓じまい」をして移転させる人が増えています。また新たにお墓を考える時に、「個別にお墓を持たない」という選択をする人も多くなっています。

前者の「墓じまい」については、お墓の遺骨を消失させるわけではなく、現在のお墓から遺骨を取り出して墓石を解体し、そこを更地にして新たな移転先に納骨するというものです。
そのためには現在のお墓の「埋蔵証明書」や移転先の「受入証明書」をお墓のある市町村役場に持参して「改葬許可書」の交付を受ける手続きが必要です。特に移転先については、承継者が不在でも永年にわたり供養してくれるお墓をあらかじめ確保しておく必要があり、場所の選定や費用などについてよく確認しておくことが大切と言えます。
後者の「個別にお墓を持たない」とは、個人スペースとして特定のお墓を持たないという意味です。私たちが実際にお墓を探してみると、自宅や遺族の住まいから遠かったり、お墓(土地)の永代使用料が高額であるなど、さまざまな問題に直面します。一般的にお墓の費用は200万円前後(都市部では300万円以上のことも)と言われます。またいつまで確かな承継者が存在するのかという不安もあります。
そこで最近増えているのが「個別にお墓を持たない」という考え方なのです。
代表的なものとしては、合祀するお墓(永代供養墓)に遺骨を納め、寺院や霊園に永代供養してもらう方法があります。
また納骨堂に納める方法や、墓石の代わりに樹木の下に埋葬する樹木葬、遺骨を粉にして海や山などに撒く散骨、さらには遺骨を自宅において供養する手元供養という方法もあります。これらは33回忌など定められた期間が過ぎた後は、永代供養墓などに合祀してもらう場合もあるようです。なお一度合祀をすると、後からお墓を作りたいと思っても遺骨を取り出すことができませんのでこの点は注意が必要です。
お墓というのは誰にとっても大変難しい問題ですね。